飯綱町に関わる人が町民ライターとなり、それぞれの目線でヒト・モノ・コトを取材して掲載しているウェブマガジン「いいいいいいづな」。昨年は年間約28万PVの閲覧数があった「いいづなコネクト」サイトの一コンテンツです。
町民ライターが、取材や原稿のスキルを学ぶ「町民ライター講座」は、毎回さまざまな方を講師にお迎えして開催しています。今回は、信濃毎日新聞社で飯綱町と信濃町を担当していたことがある記者・岩安良祐さんに、インタビューの心得を学びました。

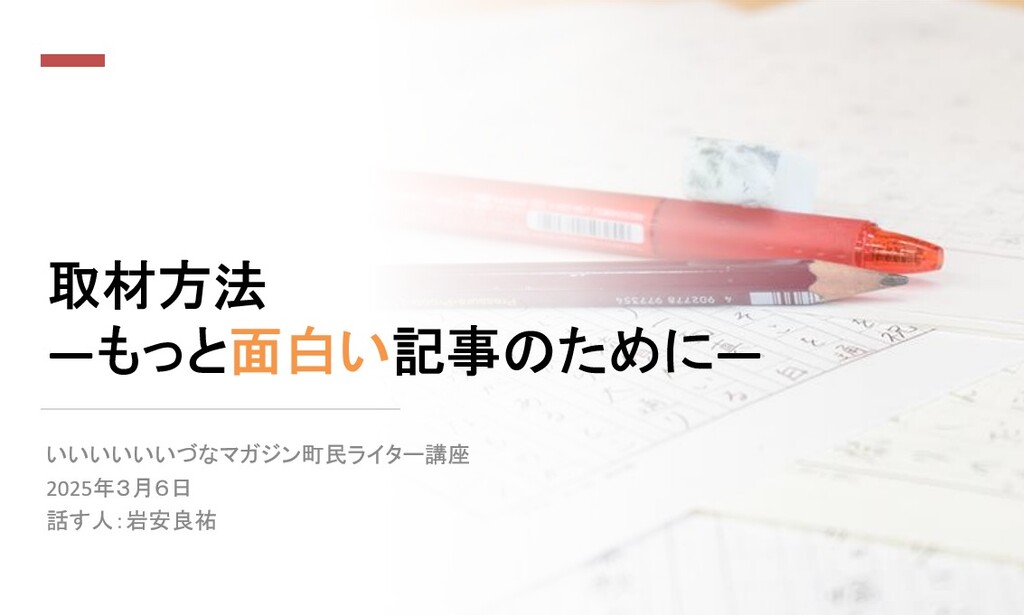
町民ライターの取材スタイル
今回の講座は、町民ライターのほか「飯綱町公民館報」の編集チームも合同で行われました。まずは、それぞれがどのように取材を進めているのかを共有しました。
「知人で面白い活動をしている方や町内のイベントを取材することが多いですね。事前に5つほど質問を用意し、取材します。必要があれば後日追加取材を行います」
「個人店を取材する際には館報を持参して、取材したいとお願いします。企業の場合はちょっとフォーマルで、連絡先を伺ってから正式に申し込みます。あえて下調べをせず、会話の中で出てくる話を楽しみにしています」
何度も取材をしているだけあって、皆さんそれぞれが独自のスタイルを持っているようですね。
次に、岩安さんは「皆さんが思う『面白い記事』とは、どんなものですか?」と、さらに踏み込んだ質問を投げかけます。参加者からは、次のような意見が挙がりました。
「知らなかった知識が増えて、最後まで読んでもらえる記事」
「考えていることが言語化されて、読み手が共感できる記事」
「読んだ後にアクションを起こしたくなる記事」

新聞記事の2つのアプローチ
では、新聞記事の「面白さ」とは何でしょうか。岩安さんは、新聞には大きく分けて2つの書き方があると説明します。
①事実を淡々と伝える
驚くような出来事や生活に役立つ情報を扱う際には、「正確さを重視し、丁寧にわかりやすく書く」ことが求められます。
②記者の視点で切り取る
人と人、場所や空間が交わることで生まれるストーリーや、身近な物事の意外な側面を描く場合は「記者の切り口や質問の仕方次第で、いかようにも面白くなる」とのこと。
この2つのアプローチは明確に区切られているというものではなく、重なり合っています。つまり、さじ加減次第でさまざまな記事が書けるということ。記事のテーマや目的に応じて、バランスを取ることが重要となりますね。
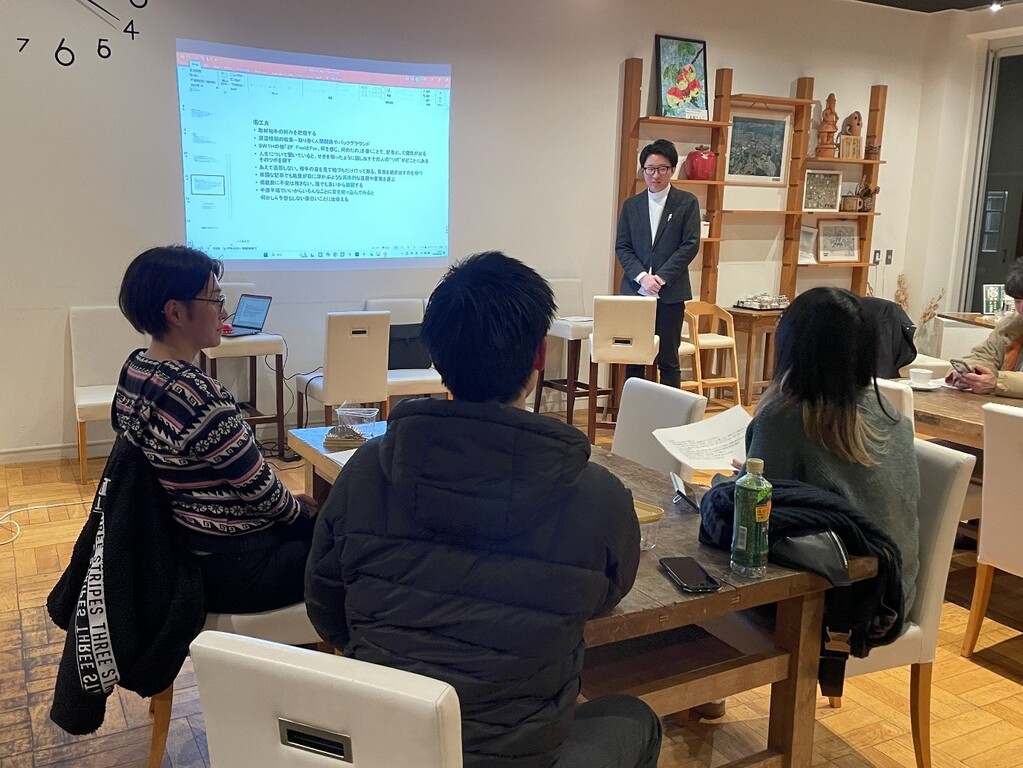
取材の本質は「知ることを楽しむ」
取材とは、単に情報を集めるだけではなく、記者自身の「心構え」が問われます。これは、インタビューの経験を重ねることで、自分の中に確立される「よりどころ」のようなもの。岩安さんに、取材において大切にしている心構えを教えていただきました。
◆「一番伝えたいことは何か?」を自分に問いかけ続ける
ポイントは、問いかけ「続ける」ということ。取材を進めるうちに、最初に想定していた切り口が変わることもあります。その変化を受け入れ、柔軟に取材を進めることが大切です。
◆取材の目的を明確にする
踏み込んだ取材だけでなく、ちょっとした取材であっても、「〇〇の理由で△△を読者に伝えたいので、あなたに取材をしたい」と、理由を明確にしておきます。相手が納得しなくても、自分の中で明確な理由を持つことが、記者としての責任につながります。
◆「私はあなたに人として興味があります」という姿勢
必要な情報を得るために淡々と話すのではなく、相手に敬意を払い、人と人として向き合います。
◆自分が思う、最も誠実なやり方で
信頼関係がなければ、取材は成り立ちません。取材対象者に対して誠実であることが、最も重要です。
◆大いなる素人として、知らないことを楽しむ
これは、元NHK記者・キャスターの大越健介さんの言葉です。前提知識がない読者の視点に立って取材し、好奇心を持ち、驚きや発見を楽しむ姿勢が、良い記事につながります。

具体的な取材方法
相手の思いをくみ取り、読者に正確に伝えるためには、取材の進め方に工夫が必要です。岩安さんの経験をもとに、取材前の準備から取材中の心がけまで、具体的な方法を教えてもらいました。
◆事前準備
記事のテーマを俯瞰して見たときの「位置付け」をします。例えば、記事のテーマが「初めての出来事」なのか、「ターニングポイント」なのか、周囲に与える影響はどうなのか……。それを整理し、書き方を工夫します。
◆取材中
取材中には、相手の伝えたいことをしっかり丁寧に、そして間違いのないようにヒアリングします。そして、前提知識が何もない読者でも納得できるように「なぜそれをするのか?」を聞きます。さらに、「あえて異なる視点や立場から質問をぶつけてみる」ことも。取材相手が気を悪くするおそれもありますが、深い話が引き出せる場合もあるそうです。
取材相手が自分の中に秘めている思いや記憶が、ふとした瞬間にあふれ出ることがあります。岩安さんはそれを「ツボ」と呼びます。
「人生について話を聞いているとき、堰を切ったように話し出す『ツボ』がどこかにあります。それを探し当て、じっくり話を聞くことが、深みのある記事を生み出すことにつながるのだと思います」
また、「相手が言葉を探して沈黙したとき、すぐに質問を重ねない」ことも重要だと岩安さんは語ります。言葉にならない想いを整理してもらう時間を持つことで、より本質的で「ディープな言葉」が引き出されることがあるからです。
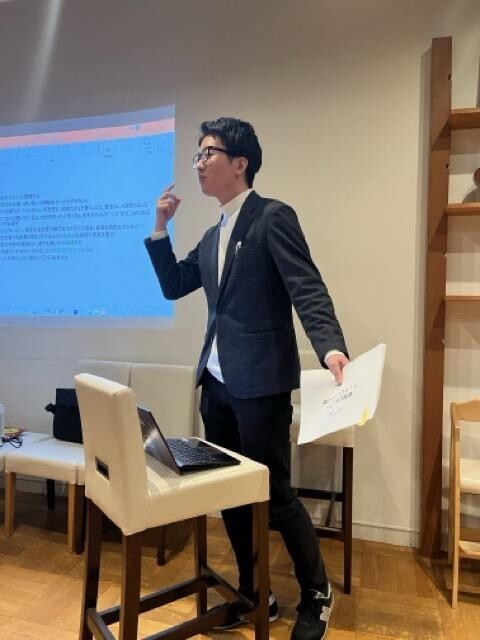
取材の個性を生み出す2F
取材では、基本の5W1H(Who/What/When/Where/Why/How)を押さえることが不可欠ですが、それに加えて2F(Feel(何を感じる)/For(何のため))という視点を持つことで、記者としての個性を出すことができるそうです。
「自分が何を感じたのか、自分が何のために記事を書くのか」という視点を加えることで記者の人間味が加えられ、より温度感があり読者の共感を得ることができる記事になるからかもしれません。
取材を断られたときは?
取材をしたくても、相手が難色を示したり、断られたりすることもあります。そんなとき、岩安さんはこう考えるそうです。
「なぜこの記事を書きたいのかを明確に伝えます。それでも難しければ、タイミングが今ではないということ。焦らず、まずは信頼関係を築くことが大切です」
岩安さんは、地域のことを知りたいと伝え、そこから少しずつ関係を築きます。そして、記事にできそうなタイミングが来たら、そのときにまたお願いするそうです。すぐに記事にすることだけを考えるのではなく、じっくりと関係を築いていくという方法は、地元に根付いた信濃毎日新聞のような媒体だからこそのアプローチと言えるでしょう。

「当たり前」を再発見! 地方メディアの魅力
冒頭の「面白い記事は?」との問いに、町民ライターの一人はこう答えました。
「この町で生まれ育った人にとっては当たり前のことでも、外から来た人の目線で見ると面白いこと、素晴らしいことがたくさんある。そういうネタを取り上げて、昔からこの土地に住んでいる人たちにも伝えたいです」
地方発ウェブマガジンの魅力は、ただ外の人に情報を届けることだけではありません。そこに暮らす人たちが、自分たちのまちの魅力を改めて感じるきっかけになることも、大切な役割のひとつです。
取材とは、知らなかったことを知り、人とのつながりを広げていくこと。その楽しさを読者に伝えることこそが、町民ライターの醍醐味なのかもしれませんね。

